| 第1話 「一通の手紙」 | ||
| 名台詞 | 「それはそうだ。しかしお父さんに言わせると、医者というものは医者を一番必要としているところで働くのが一番の生き甲斐であり、それが医者としての使命であると思うんだ。このベルン市には他にいくらでも医者がいる、お父さんがいなくたって大して困りはしない。生活が贅沢で、太りすぎたり糖尿病にかかったりする人の面倒を見るよりも、新しい国で一生懸命働いて病気になった本当に医者を必要としている人たちの面倒を見る方が、どれだけ有意義か知れない。」 (エルンスト) |
名台詞度 ★★★★ |
| 子供達にオーストラリア行きの誘いが来た事を打ち明けた父エルンスト、これを聞いた長男フランツは「断ればいい」と大きな問題と考えない。なぜなら父が仕事に困っているわけでもないし、今の仕事が繁盛しているからだ。これに対して父はこのような言葉で反論する。 この台詞には「仕事は金や儲けだけでない」というこの男の信念が見てとれる。恐らくこの医師は、冒頭で出てきた診察シーンのように太り過ぎとかそういう贅沢な悩みの患者ばかりなのに嫌気がさしているのかも知れない。一度そうなってしまうと本当に自分を求めている場所というのを探したくなる、この台詞にはそんな「現状には満足していない」男の思いというものが込められている。 もちろんまだ若いフランツにはその気持ちは分からないし、私もこの台詞の奥深さは大人になった今だからこそ理解できる。本当は二つ返事で「行きます」と返答したい父の本心、それと家族の存在と板挟みになっている苦悩。こんなこの台詞は大人になって初めて分かる思い台詞なのだ。 |
||
| 名場面 | 逆立ち。 | 名場面度 ★★★ |
| 「家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ」という物語が幕を開いて最初のシーンと言ってもいいだろう。物語の最初の舞台となるベルンの町の説明があった後、最初のシーンは主人公フローネが通う学校シーン。しかも下校時刻で級友に呼び止められるフローネ、こんな何でもない平和な日常から物語が始まるが、この物語を一度でも全部見たことがある人間にとっては違和感があるシーンだろう。 そしてフローネと眼鏡を掛けた友人の話題は、逆立ちの話題となる。この友人の前で逆立ちするのか?と思ったら、すぐこの友人と別れてしまう。だが一人になったフローネはその公園とおぼしき芝生で一人逆立ちに挑む。すぐにワンピースが垂れ下がってきて視界が奪われ、転倒する。そして「つい夢中になってやり過ぎちゃう」と自分の欠点を語り出す。 まさに「つかみはOK!」と言いたくなるシーンだ。フローネという少女の性格を、短い時間で上手く印象付けていると思う。これをみたら誰も「フローネは無口でお淑やか」だなんて思わないだろう。このシーンでお転婆で活発な少女であると強く印象付けるからこそ、今後の彼女の行動が全て生きてくるのだ。   |
||
| 感想 | 「ふしぎな島のフローネ」は再放送が多かったので何度も見た記憶があるが、最後に見たのが中学1年頃だったと思うからかれこれ28年ぶりくらいに全話通しで視聴することになる。いやぁオープニングの「♪ちゃらっちゃちゃちゃらっちゃ〜」がとても懐かしかった。そしてこの第一話も良く覚えている。今後の物語の展開が走馬燈のようによみがえってきたぞ。 名場面シーンに上げた冒頭シーンのフローネはもう「いかにも」って感じで良い、てーかこのシーンで彼女が印象付けられた訳だ。それにエルンストの名台詞は今だからこそ分かる深い台詞、恐らくこの感想欄や名台詞欄は「大人になってこそ」というものが多く挙がってくるだろう。なんてったって本放送は小学4〜5年生時、再放送で見た時だってフランツより若かった頃なんだから「大人の目線」で全話通し視聴に挑めば印象は大きく変わると思う。 その中でもエルンストの心境というのが大人になって見るととても印象に残る。詳細は名台詞欄に書いた通りだが、こういう自分の意志と現状の板挟みで揺れ動く大人の姿というのを、包み隠さず描いたのはやはり「世界名作劇場」シリーズの良い点だと思う。今時の作りだったらこの父親は特に悩みもせずに決断を下したであろう。 しかしいつ見ても思うのだが、この物語のフローネとジャックの年齢設定がちょっと間違っているようにも感じる。公式にはフローネ10歳、ジャック3歳ということだがどう見てもこの二人は年齢相応の言動を取らない。フローネはどう見ても7〜8歳児の言動を取るし、ジャックは姿形も含めて5〜6歳程度だ。実はこれは少年時代に再放送を見た時に感じた事で、自分の従兄弟達と比較して感じた事だ。 |
|
| 研究 | ・ベルン 物語はロビンソン一家の故郷、スイスのベルンからスタートする。ベルンはスイスのベルン州の州都で現在の人口は約13万、スイスではチューリッヒ、バーゼル、ジュネーブに次ぐ第四の都市であるだけでなく、スイス連邦議会が置かれている等スイスの首都であり、万国郵便連合などの国際機関も置かれているスイスの中枢である。 ちなみに「ベルン」というのは英語読みで、フランス語では「ベルヌ」、ドイツ語で「ベァールン」ということらしい。このドイツ語の「ベァー」がこの町の名前の語源で、この町が開かれた頃に公爵が熊を殺したことでこの名前が付けられたと言い伝えられている。 劇中に出てくる町並みは現在もほぼそのまま、中世ヨーロッパの都市の景観を守っている。「ふしぎな島のフローネ」放映翌々年に当たる1983年にこの町並みは世界遺産に登録された。ベルンの町は12世紀頃に開かれたのだが、1405年に大火を経験して現在見られる石造りの建物が多くなったのだという。また文学作品や美術作品の保護に関する「ベルヌ条約」もこの町で作成された。 |
|
| 第2話 「旅立ち」 | ||
| 名台詞 | 「僕も行く、オーストラリアへ!」 (フランツ) |
名台詞度 ★★ |
| だがいよいよフランツ以外の一家がオーストラリアに旅立つその時、一家に声を掛けられても何の返事もしないフランツだったが、いよいよ一家を乗せた船が動きだすとそれを追って飛び乗る。驚く一家に一言こう言うのだ。 実はこれがフランツの本心だったのは言うまでもない。フランツの本音は「何処へ行くにしても家族と一緒」と言う事だろう。その証拠に家族会議で彼は自分の処遇が決まった際、素直にそれに応じるのでなく驚いた表情をしているのだ。つまり家族が離ればなれになる事は彼の本心ではなく、自分の将来の夢よりもそれは優先されるべき事だったのだ。 さらに言うと、彼は音楽の勉強ならばオーストラリアでもできると踏んでいたのかも知れない、もしくは自分がその先駆者になる覚悟が心の中であったのかも知れない。その部分の本心は分からないが、彼が約束された未来より家族を取ったことだけは確かで、これが今後の物語を盛り上げて行くことだけは確かだろう。 |
||
| 名場面 | 家族会議。 | 名場面度 ★★★ |
| オーストラリア行きの決心がなかなか付かないフランツをよそに、両親はその準備を着々と進めていた。「もう一度家族会議を行い、反対者がいれば中止」となるはずだったオーストラリア行きだったはずなのに裏切られたとフランツは感じ、その反発心からフランツは家族会議でオーストラリア行き反対を決意する。その中で家族会議がエルンストの弟夫妻も出席して開催された。ここで両親はもう決意は固いことを表明した上でフローネとフランツの意見を聞くことになる。無論フローネは賛成だが、フランツは「僕の意見を言っても無駄だ」「もう叔父や叔母がこの家に住むことまで決めてしまった」と反発し、本心を語ろうとしない。両親がそれでも自分の意見を言うように促すと、フランツは立ち上がって「反対」を表明する。 エルンストは「一人でも反対者があればこの計画は中止と言ったが、計画を変更する」と宣言し、フランツのみベルンに居残り、叔父や叔母、それにお手伝いのマリーと暮らすという結論を下す。この沙汰を聞いたフランツは声を上げて驚く。 フランツの言う通り、既にオーストラリア行きの話は覆すことが不可能であった。だが両親はフランツにはしっかりと選択権を与えていて、家族と一緒に来るか自分の夢を叶えるかの二者択一を取らせることにしたのだ。そう、もうフランツは十代も半ばなのだから自分の将来について自分で判断しなければならず、その責任も自分で取らねばならないと判断したのだろう。エルンストが「フランツは子供でない」と言い切ったのはその辺りが理由だ。だがフランツの本心は別のところにあり、それは名台詞欄を参照して頂きたい。 しかしこのシーン前後のフランツを見ていると、アムロとダブる…。   |
||
| 感想 | 物語は前半と後半にうまく分かれた。前半ではフローネがオーストラリア行きの話を学校の友達に言いふらしたことから、ロビンソン家のオーストラリア行きが街中の噂になってしまう展開。この中でアンナとフランツの「心の迷い」が上手く描かれているが、フランツについては後半への伏線になっていたがアンナの心の迷いは有耶無耶にされてしまっているような。これが解決する話が入るのかと思ったらフローネとお手伝いのマリーの話になって…この2人の話は不要ではない、家族会議のシーンや旅立ちを盛り上げるために必至だからだ。 そして後半はフランツの話になる。いやぁ、今回のフランツは「哀戦士編」前半のアムロとダブるダブる。フランツとアムロは担当声優が同じと言うだけでなく、性格も似ているだろう。そしてアムロはガンダムのパイロットとして戦地へ出て行くことによって、フランツは無人島でのサバイバル生活を通じて一回りも二回りも成長するという点も共通点だ。だからこの2人を担当している古谷徹さんは、こういう我が儘だけど成長する若者という印象が強くなったのは、「ガンダム」だけでなくてこの「ふしぎな島のフローネ」での印象も理由にあるのだ。 話は前後するが、この前半のフローネの行動については私は心当たりがあって当時も恥ずかしい思いがした。一時期私の父が転勤になって引っ越すかも知れないと家で話題になったことがあって、私が決まったわけでもないのに学校の友達に話してしまった経験があるのだ。その転勤は回避されたのだが、自分が引っ越すという噂だけがしばらく残って、今思い出しても穴があったら入りたくなる。 |
|
| 研究 | ・ |
|
| 第3話「フローネの心変り」 | ||
| 名台詞 | 「私、オペラ歌手になるのやーめた。私やっぱりみんなとオーストラリアへ行くわ。でも誤解しないで、私に歌の才能がないからじゃないのよ。食べたいものが食べられなかったり、思い切り遊べなくなるのが嫌だからよ。」 (フローネ) |
名台詞度 ★★★ |
| ライン川を下る船上でロビンソン一家はルイーゼコップというオペラ歌手と出会う。その前にゲルハルトと名乗るどう見ても怪しい自称音楽家に歌を褒められ有頂天だったフローネは、歌の勉強をするためにやはり残留するときが変わる。だがルイーゼコップにゲルハルトの正体を知らされ、それによって自分の才能も嘘だったとふさぎ込むがまだ諦めていない模様だ。だが一家と一緒に食事をすることになったルイーゼコップが喉を守るために食事は制限し、不摂生な生活もしていない事を語るとフローネが突如立ち上がってこう宣言するのだ。 この台詞でフローネの性格が確定したと言っていいだろう。物語序盤で登場人物の性格が少しずつ印象付けられる段階で、それぞれのキャラクターについて性格を印象付ける決定的な台詞というのはどんな物語にもあるものだ。フローネの場合はまさにこれ、この一言でフローネの「お転婆」以外の性格が強く印象付けられることになる。それは天真爛漫で食べることが大好きだという印象だ。こういう印象の少女が、学校の成績も良いはずがないという予測までできてしまうすごい台詞だ。 この台詞を聞かされた一同は大笑い、ルイーゼコップはフローネの肩を抱き「それでいいの」という頷きを見せる。このフローネの子供らしい無邪気な明るさは、今後物語が殺伐としてくると大きな救いになってくる。それまでも予感させてくれるのだ。 |
||
| 名場面 | マリーアントワネットとモーツアルトの逸話。 | 名場面度 ★★★★ |
| 物語はもう既に「旅」に入っている、だがこの物語では「滞在地」での物語で繋ぐわけにはいかない。事が起きるまでは「移動中」にどのようなエピソードを入れて退屈させない作りにするか、これが序盤での命題になってくるわけだ。 ここで川の中に浮かぶ中州を見つけ、エルンストはこの中州にまつわる話としてマリーアントワネットの嫁入りについて語る。それはオーストリアとフランスの国境にあるライン川のこの中州で、14歳のマリーアントワネットが全裸でフランスに引き渡されたという話だ(もちろん14歳のマリーアントワネットで全裸で出てくる、名場面に選んだのはこのシーンがあるからではないことを明記しておこう)。その話を受けてフランツは、音楽好きらしく幼少期のマリーアントワネットとモーツアルトの逸話について語る。どちらの話もキチンとアニメで再現され、手の込んだ作りになっているのは感心だ(14歳のマリーアントワネットの全裸をご覧になりたい方はDVDを買うなりして頂きたい)。 これらの逸話がうまく劇中に入れられたことは今見直してみると感心する。こうして本放送当時の子供達は自然に世界史に触れ、フランス革命等の歴史に興味を持つきっかけになったのだ。興味を持たずともうんちくとして記憶に残り、何処かでマリーアントワネットの話題が出てきたときに得意げに語ることも出来ただろう。 どちらの逸話もマリーアントワネットについて調べたことがある者なら知っていて当然のものだと思う。ちなみにこの中州はストラスブール(フランス側)とケール(ドイツ側)の間に位置するそうだ。マリーアントワネットについてこれ以上詳しく書いたら、完全に脱線する上いつ終わるか分からなくなるので、次行こう。   |
||
| 感想 | 一家が移動しているだけで特にこれと言って何もない話ではあるが、名場面欄に記したように「特にこれと言って何もない話」で視聴者を退屈させない作りにするのは難しいのである。しかも物語はまだ序盤の第三話、ここで視聴者が退屈するようなら即座に逃げられてしまい打ち切りの危機が訪れることになる。そこに退屈しのぎにマリーアントワネットの話題を差し込むのは本当に上手く考えたと思う。 また物語のもう一つの流れとして、ライン川の船上で詐欺師に騙されかかる展開だろう。でもこれは本物のオペラ歌手が出てきて一件落着というのはこれまた面白い。その過程でフローネが有頂天になり、真実を知って立ち直るまでの過程もこれまた面白い。この話を見てこの物語の先行きに期待したという人は多いだろう。 |
|
| 研究 | ・一家の旅程その1 いよいよ一家がオーストラリアへ向けて偉大なる一歩を踏み出した。この物語では第一話と最終話以外の48話に渡ってベルンからオーストラリアへの移動を描いていると言う事も出来るだろう。ま、足踏みしている期間も長いが。 今回はライン川を下る話が主体である。今回の冒頭でフローネがナレーターとして当面の旅程を語る、その内容は「ライン川に出てから別の大きな船に乗り換えたの、この船でオランダのロッテルダムまで下り、そこからまた別の船でイギリスのリバプールに渡り、リバプールからさらに大きな船でオーストラリアへ向かうわけ」とのこと。 このフローネの解説を地図に示してみると、このようなコースとなる。ただこのルートだとちょっと不自然なのがロッテルダム以降のルートだ。リバプールはグレートブリテン島の西側に位置するので、フローネの解説通り「ロッテルダムからリバプールに渡った」とするとこのようにグレートブリテン島をぐるりと回らなければならない。リバプールは世界で最初に鉄道が敷かれた町の一つでもあり、世界最初の鉄道がリバプールの近くのマンチェスターを中心に路線が延びたことを考えると、グレートブリテン島の東側の港にたどり着いて陸路リバプールに向かったと考えるのが自然だ。だが今回だけでなく、次話の解説でもイギリスで鉄道に乗ったという解説はされず、またそのようなシーンも描かれていないし、むしろ次話冒頭のナレーションではロッテルダムからリバプールまで直行したかのような解説だったために、グレートブリテン島をぐるりと半周する船便に乗ったと解釈せざるを得ない。 その行程は約2400キロ、東京を基準にすればどっちへ向かっても日本列島からはみ出してしまう距離を既に消費したことになる。その距離の半分はロッテルダムからの海路であり、今回の劇中で描かれた船はだいたい1000キロ程度の旅という事になったのだろう。途中で燃料と水を補給しながら二昼夜はあの船に乗っていたと考えて良いと思う。なんかこの第三話ってちょっとしたピクニックみたいな感じに描かれていたが、既にこの時点で大旅行の域に入っているのである。 現在なら鉄道と船でもっと短時間で移動できるだろう。てーかこの「ふしぎな島のフローネ」の年代が、未だによくわからない…。 |
|
| 第4話「オーストラリアめざして」 | ||||||||
| 名台詞 | 「あなた、人間はいつ何時どんなことが起こるか分からないのです。ですからあなた、普段からどなたに対しても広い心を持ってお付き合いしなければなりません。これからは、他人様に対してもっと広い心を持って下さいね。」 (キャサリン) |
名台詞度 ★★★★ |
||||||
| オーストラリアの役人でもあるエドワードの妻、キャサリンの帽子がジャックがいじっている間に風で飛ばされるという事件が起き、エドワードはジャックの父であるエルンストに酷い言葉を掛ける。それから何日かした赤道祭の日にキャサリンが産気付くが、船医が酔いつぶれて使い物にならなかったためエルンストがこれに対処、無事男の子が生まれた。妻と子供の生命を救ったのがエルンストだと知って狼狽えるエドワードに、妻キャサリンが訴えた教訓がこの台詞だ。 そう、彼女が言う通りいつどんな状況で誰に助けられるようになるかは分からない。だから誰にも親切にした方が良いのは当然だ。威張って他人に冷たく辺り、冷徹な対応をすれば困ったときに誰も助けてくれなくなる。特にここは狭い船の上だ、長期間に渡って限定された同じ人々と付き合わねばならないのだから当然のことである。エドワードという人間は自分の地位に溺れてこんな基本を見逃していたのだろう(皆に偉功を示すなんて言ってるようじゃ…)、妻がこれを忘れずにいたのだから幸せな男であることは確かだ。 この台詞に対し、エルンストは「いい教訓を得た」と評し、船長は「長い航海だ、みんな仲良くやって下さい」と言う。こんな教訓をも投げかけてくれるテレビ番組って、最近見てないなぁ。 |
||||||||
| 名場面 | エドワードvsエルンスト。 | 名場面度 ★★★ |
||||||
| ジャックが悪戯している間にキャサリンの帽子が風で飛ばされ、怒り心頭のエドワードはフローネに「親を呼べ」と怒鳴る。そこへ現れたフランツが船室に戻りエルンストを呼んでくると、二人の対決が始まる。「申し訳ありません、どうかお許し下さい。帽子は弁償いたします。高価な帽子とは思いますが、仰るだけ弁償させて頂きましょう」「金など貰っても仕方がないんだ、あの帽子はパリで特別作らせた物だ」「このお金でパリの同じ店で、同じ物をお作りになって下さい」「ふっ、バカだねお前さんは、我々はオーストラリアに向かって大西洋のど真ん中にいるんだ、どうやってパリに注文する?
私は妻がメルボルンに降り立つときにあのパリ仕立ての帽子をかぶっていてもらいたいんだよ。どうしてくれるね?」「それは…」「では泳いでいって帽子を拾ってきたまえ」「そんなことが出来ないことはお分かりでしょう?
私に出来ることならどんなことでもいたします」「では、その悪戯坊主を鞭で100回打ってもらおうか?」「それでは、この子の代わりに私を鞭で100回打って下さい」「そうしてもよいが、あいにく鞭がない。その方、妻の靴に口づけしろ、それで許してつかわそう。どうかね…」、こう言われてキャサリンの前に跪くエルンストだが、キャサリンが止めて一件落着。 このシーン、「敵に回してはならない人を敵に回してしまった」感が強く出ていて好きだ。さらにこの長い船旅を不安にさせる要素も含んでいて、恐らく嵐が来る前の段階では最も緊張するシーンであるだろう。と同時にキャサリンが身重だという事実と、使い物にならなそうな船医を見ていると、エルンストの活躍で汚名返上されることも容易に想像が付くことになる(名台詞欄)。 さらに言うと、ここでのエドワードの演技が意地悪な男として最高の物だ。「ふっ」と後に「冗談はよせ」とか言い出したり、「敢えて言おう、カスであると!」と演説ぶりそうで怖かったけど。いずれにしろ2人の男の性格が良く見えていて、双方のキャラクター性を充分に活かした対決シーンで見ていて迫力があった。   |
||||||||
| 感想 | 何度目かの再放送を見た時に感じた事をまず書いておこう、この船、ギレン・ザビが乗ってる…。エドワードの担当声優は「世界名作劇場」シリーズと「ガンダム」シリーズでお馴染みの銀河万丈さんだ。この人、「世界名作劇場」ではあまり意地悪な役をやっていなかったので、こちらでは「小公女セーラ」のラルフのような優しい父親像として印象に残っていることが多い。だけどこのエドワード役ではギレンに近い「偉い人」の演技だ。ま、途中からはペンデルトン(「ポリアンナ物語」)のようなネタキャラに変化するから面白いけど。こういう短時間でいろいろなキャラへ変化して行く人というのは、「旅もの」ではなくてはならない存在だ。その人の「変化」が自然であれば自然であるほど、物語を退屈にさせない要素となるのである。 というのも、今回も全話に引き続きあくまでも一家の「移動」のみを描いており、これでいかに退屈させないかが問題となる回なのだ。「船での長距離移動」を描くとなれば運命を共にする乗り合わせた人との物語を描くことになり、これを単なる一過性の友達付き合いでなくキチンと「ドラマ」として見せねばならない。これが一家とエドワード夫妻の話だったり、フランツとエミリーの関係だったりするのだ。 そして今回は船長や飼い犬のジョン、それに乗っている動物たちをさりげなく印象付ける回でもあるのだ。船に問題があれば船長の動きというのは重要になってくるし、この時点ではまだ分からないがジョンや動物たちも今後の物語で重要な存在になって行く。その点をさりげなく示唆したという点においては、うまく出来ていると感じた。 もう一人ネタキャラが船に乗っていた、それはマシュウの声のデイトン先生(笑)だ。船上での生活の様子を「南の虹のルーシー」のキャラに置き換えて想像してみるのも面白いかも知れない、ポップル一家もこんな経験をしながらアデレードに向かったのだと考えるだけで楽しいものだ。 |
|||||||
| 研究 | ・ブラックバーンロック号 イギリスのリバプールに到着した一家は、いよいよオーストラリアへの移民船である「ブラックバーンロック」号に乗り込んでメルボルンを目指す。ここで出てくる船は立派な外洋船で、外輪式の蒸気船である。「南の虹のルーシー」に出てきた移民船と同様、帆船に蒸気機関を付けたような形となっていて風があるときは風力によって進むことで燃料費を節約していたのだろう。 船の大きさは劇中の様々なシーンから想像することが出来る、だいたい全長70メートル、全幅8〜10メートル程度、喫水線からの全高は40メートルといったところだろう。現在の中型フェリーと同じ程度の大きさと考えればイメージがつくと思う。ちなみに「南の虹のルーシー」の際に移民船の大きさを割り出せなかったのは、意外にも移民船が画面に出てくるシーンが少なかったことが理由としてあげられる。なにせ移民船の全景が出てくるカットは下記に示した一回しかないのだから。 この「ブラックバーンロック」はリバプールとメルボルンの間の定期便でもあるようだ。ロビンソン一家のような移民だけでなく、エドワードのような役人の往復にも利用されている事からそう考えることが出来る。船室の様子についての描写は少ないが、この時代の定期船で移民船でもあることを考えると1等・2等・3等という船室区分があったと考えられる。ロビンソン一家やエドワード夫妻が乗っていたのは個室でかつ装飾が少ない点などが想像すると、2等船室であった可能性が高い。もちろん船の中には贅を尽くした1等船室や、蚕棚のような寝台が並んだ3等船室もあったことだろう(「南の虹のルーシー」第1話で出てきた船室がこの時代の3等船室と思われる)。 乗船時は劇中に描かれた通り、乗客はボート、荷物は艀を介して沖に停泊している船に乗り込むかたちだ。これはリバプール港の水深が浅かったり、桟橋設備が貧弱で大きい船が着岸できない等の事情があったのだと推察される。下船時は「南の虹のルーシー」第1話のように、遠浅の砂浜の沖合に停泊して人も荷物もボートを使って上陸することになる。 リバプールからメルボルンまでの所要時間には触れられていないが、「南の虹のルーシー」ではイギリスからアデレード近郊まで3ヶ月を要したことが語られているので同じ位掛かったと考えて良いだろう。 この船についての考察については、「南の虹のルーシー」第7話の考察も参照して頂きたい。
|
|||||||
| 第5話「フローネ船長」 | ||
| 名台詞 | 「お母さん、私はお父さんもお母さんも愛しているの。だから2人に別れて欲しくないの!」 (エミリー) |
名台詞度 ★★ |
| み、耳が痛い。 | ||
| 名場面 | フローネ司厨長。 | 名場面度 ★★★ |
| エミリーを両親の離婚の危機から救うという使命を成し遂げたフローネは、船長を辞めて司厨長に役職を変更する。この人事変更は船長だったときの権力を行使して行ったことだろう。そして司厨長の立場を利用して自分が好きなケーキを作らせ、ケーキをホールごと食べようとするが…。 このシーンのフローネが心の底から楽しそうで、見ているこっちまで楽しくなってしまう。巨大なケーキもとても美味しそうに描かれており、それを普通に食べるのでなくあくまでも「つまみ食い」風に少しずつ、しかも不定形に切り取って行くのがいい。子供の頃、多くの人たちはこんなケーキの食べ方を夢見ただろう。 もちろんこのシーンが秀逸なのは、フローネがやりたい放題好き勝手やってそれで終わらない点だ。フローネはこのシーンの後、食べ過ぎで腹痛に苦しんで医師である父から診察を拒否され、皆の笑いものになると言う「オチ」を演じさせられることになる。好き勝手した以上はちゃんと因果応報がまっているという事を、子供達に教えるシーンでもあろう。   |
||
| 感想 | さ、いよいよフランツと船長の会話に「嵐」というキーワードが来た。物語が「本編」に入るのはもう近いぞ。 その前に今回は一話完結ストーリーで、最後の大笑いの展開を入れてきた。エミリーには悪いが、エミリー両親の離婚騒動はこのロビンソン一家の底抜けの面白さを強調するために用意されたと言っても過言ではないだろう。特に権力を得て得意になるフローネや、ラストシーンでのフローネの醜態を語る両親の姿は本当に面白い。この両親がいるからこそ、ガキ共がこんな面白いんだろうなと思わせてくれる一話だ。 特定の船客、しかも子供に一日船長をやらせるというのはアニメだから許されることだろう。これってアイドルが一日警察署長や一日消防署長をやるのとは訳が違う、当時の船なら船長というのは一国の主と同じ位の権力を持っているはずだからねぇ。でもそんな野暮な話はなしだ。それより序盤のみんな船旅に退屈している様子の描写がこれまたよかった。船って結構退屈な乗り物なのよ、それは舞鶴から小樽までの30時間の船旅で知った事実だ。 今回、ジャックがジョンと遊んだシーンも印象に残ったが、それは研究欄で…。 |
|
| 研究 | ・ジョンが走るスピード 今回の序盤で、船長の愛犬であるジョンがジャックを背中に乗せて船の中を走り回る。犬が人を背中に乗せて走るという行為が正しいかどうかは別にして、このシーンを見ていて昔から気になったことがある。そこで今回、大胆にもこのときのジョンの走行スピードを算出するという暴挙に出ることにしてみた。 算出に使った画面は甲板を上から見たシーン、背中にジャックを乗せたジョンが甲板より一段高い回廊状の通路を走り回るシーンだ。ジョンはこの回廊を一周5秒ジャストで駆け抜けている。この回廊の距離が分かればジョンのスピードが算出できる。 前話感想欄のキャプ画から推察してみると、この高さでの外輪カバーの外径は約7メートル、全幅は外輪まで含めずに10メートル程度、外輪カバーの横幅は2メートル程度だろう。外輪の半分が舷側の外に出ているとすれば、外輪カバー間の内径は8メートルとすることができる。通路の幅を1メートルとすれば、ジョンが走った回廊の通路中心での形状は長さ6メートル、横幅7メートルの長方形と推測できる。下のキャプ画と比較すると長さがもっと小さく、横幅はもっと大きそうだが、そうすると外から見た船のサイズが大きく変わってしまうので劇中に出てくる「船を外から見たシーン」に従うことにしよう。 そうすると通路の長さは1周26メートル。26メートルを5秒で走ったと言うことは秒速5.2メートルということだ、時速にすれば18.72キロ。ママチャリを全速力で漕いだくらいの速度なので不自然ではないだろう。意外にきっちりとした速度が出てきたなぁ。 「クレヨンしんちゃん モーレツ!オトナ帝国の逆襲」でしんのすけが走る速度を研究したが、これとの比較は意味が無いだろう。人間の5歳児と犬が走る速度を比較する意味を感じないのだ。それだけでなく走る目的も違う。しんのすけの場合は敵を追うという目標と共に、上へと続くタワーを登るというどちらかというと持久的な走りをしなければならない。だからこそ箱根駅伝のランナーと比較するのに意味があるのだ。だが今回のジョンは、単に遊びとして走っているに過ぎない。疲れれば走るのをやめればいいのだし、距離にも目標はない。だから短距離走的な走り方で充分だろう。 あ〜、不自然な結果にならなくてよかった。 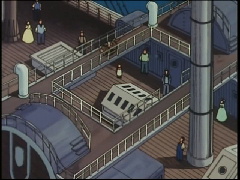 |
|
| 第6話「こわい嵐」 | ||
| 名台詞 | 「フローネ、神様のことをそんな風に言ってはいけません。たとえ何が起ころうとも、神様を悪く言ってはいけません。神様は何事も深いお考えがあってなされるのです。ノアの洪水が何故起こったか知ってるでしょ?
この嵐も私たちの心の奢りを罰するためかも知れません。よく胸に手を当て、もし心に奢りがあったら悔い改め、嵐が速く収まるようにお祈りをしましょう。」 (アンナ) |
名台詞度 ★★★★ |
| 嵐に巻き込まれた船は木の葉の如く翻弄され、ロビンソン家の船室ではついにアンナが船酔いで寝込んでしまう。そんな母親をよそにフローネとジャックは珍しい嵐にまだはしゃいでいる段階だ。このとき、ジャックがクリスマスの劇の「私は主の御使いだ」という台詞を思い出す。それに呼応してフローネが「主もとんだ事をしてくれるわね」と叫ぶと、アンナが半身を起こして娘達にこう説くのだ。 フローネの言い分は「クリスマスイヴにこんな嵐を起こすから」と言う事だが、そんな巡り合わせもしっかりと受け止めねばならないと母は説くのである。この嵐は神の考えによって自分達に与えられた試練だとし、それを治めて貰うには祈るしかないという論理だ。「何事も神の思し召し」というキリスト教的考えであり、日本的考えとは違う一神教的の論理で試練を乗り越えることを説く。 この台詞に対して部屋にいた一家はアンナと共に神に祈りを捧げる。航海の無事と一家の安全を祈って…だがこの嵐が一家に与えられる試練の入り口でしかないことは、まだ誰も想像だにしていないだろう。 この「神の思し召し」という論理は「世界名作劇場」で多く語られることで、特に「わたしのアンネット」では強調されているように感じる。その中でもこの嵐の中、神にも見放されつつある状況でこの考えを実行しようとするロビンソン一家の行動には最も説得力を感じる。過酷な状況にいる人たちはこのように考えることで、神が隣にいて手を引いていると考えることで試練を乗り越えるのだ。自然が豊かな日本的文化(神は全てのものに宿っている)では出てこない論理だ。 |
||
| 名場面 | 最後の救命ボート | 名場面度 ★★★★★ |
| 海難シーンで一家が孤立する決定的瞬間となるシーンだ。船員の手伝いに行ったフランツ以外の一家は、船室の中で船に起きた異常を感じ取る。船が大きく傾いて揺れが収まったという変化だ。この状況に特に誰が言い出すまでもなく甲板へ上がることにした一家だが、傾いた通路や階段に苦労して上がった甲板で見たものは、人々が救命ボートで船から脱出しようとしている光景であった。甲板が波に洗われているのを見たエルンストは「座礁した」と状況を判断し、一家も脱出すべく甲板を滑って救命ボートに接近する。 その救命ボートで手を振る人影があった、それはフランツのガールフレンドであるエミリーだ。エミリーは担当の船員にロビンソン一家も乗せるよう懇願するが、一家はなかなか救命ボートに近づけない。そうこうしているうちに船が大きく傾いで、船員が慌ててボートを下ろし始める。エミリーは「このボートが最後だから」と懇願するが、救命ボートは無情にも海面に降りて行く。下りつつあるボートからエミリーが叫ぶ、「フランツは何処!?」。一家はフランツの行方が分からなくなっている事実にここで気付くのだ。嵐の海に響き渡るエミリーがフランツを呼ぶ叫び声、一家も「フランツは船の何処かにいる」と判断してフランツの名を呼び続ける。 嵐によって船が末期的状況を呈し、その緊張感が上手く表現されている。特に「救命ボート」というやつは海難シーンを盛り上げる一番の要素で、映画「タイタニック」でもこれが存分に活かされているのは言うまでもないだろう。そしてロビンソン一家に退船指示が伝わっておらず逃げ遅れる設定、それでもなおかつ最後の救命ボートに間に合うか否かという状況、そのタイミングで突然傾ぐ船、さらに行方不明の家族…序盤で最大の見どころである海難シーンはこのシーンで最大の盛り上がりを見せる。そしてついに一家は置いて行かれ、いよいよこの一家5人だけの物語へと変わって行く瞬間なのだ。 またこのシーンだけでなく、この嵐全般もものすごい迫力で描かれている。「世界名作劇場」シリーズにおける悪天候シーンでは、この嵐と「わたしのアンネット」におけるルシエンの峠越えが強く印象に残っている。このふたつは「世界名作劇場」で極限の気象条件を描いたものであり、これ以上の物は他には考えられないだろう。船を襲う大波や横殴りの雨、それに絶え間なく続く風の音や人々の悲鳴だけでなく、甲板シーンではわざとピンボケで描いて大雨による視界不良までも演出している。名台詞のシーンなんか見ているこっちまで船酔いしそうだったもんなぁ。    |
||
| 感想 | 唐突に物語は「本編」への扉を開ける。「こわい嵐」というサブタイトルだけで本編突入が予測される展開だが、それだけで1話を消費しきるのでなく前半は航海中の楽しいクリスマスを描くことで悲惨な嵐と対比させる役割があったのだろう。この一話は本放送で見た記憶もハッキリ残っていて、嵐のシーンの大迫力とその中で必死になっている登場人物に心を奪われたものだ。特にラストの救命ボートのシーンはよく覚えていた、エミリーがフランツの名前を叫びつつ画面から消えることも。 そしてこの回をきっかけに物語は「旅行記」から「漂流記」へと展開を大きく変える。だからこそここからが「本編」と言えるのだ。 それと本放送でこの回を最初に見た時、真夏のクリスマスシーンというのに強い違和感を覚えたのも記憶に残っている。この時は「南半球だから夏と冬が逆」と理解して見ていたのでなく、単に熱帯地方の海の上だからクリスマス時期でも暑いのだと理解していた記憶が。そういえば南半球が舞台の「南の虹のルーシー」ではクリスマスの話はなかったなぁ。いずれにしてもクリスマスは真冬にやらねばならないのでなく、12月25日という日付けが大事だと言う事はこの時によく理解した。 |
|
| 研究 | ・海難事故 いよいよ船が海難事故を起こす。フローネ達を乗せた「ブラックバーンロック」号が熱帯低気圧に遭遇し、その波浪の中で機関停止という壊滅的状況に陥った上に岩礁に乗り上げ、船体を大きく破損する事故を起こしてしまったのだ。この事故で生き残った乗組員や船客は救命ボートで脱出するが、ロビンソン一家は船から脱出する機会を逸して孤立する。そして物語はいよいよ本編となる「漂流記」部分へと入って行くのだ。その入り口になる海難事故について、数回にわたり様々な方面から研究してみたい。 まずは海難事故の過程を詳しく追ってみよう。「ブラックバーンロック」号が熱帯低気圧に遭遇したのは12月24日であることは間違いない。それは船客によるクリスマスイベントが行われた日であったこと、フローネが「クリスマスイヴにこんな嵐を…」と語る点から明白だ。劇中の台詞を拾ってみると、それから5日間はずっと時化の中にあったことが分かる。その間に機関室への浸水、落雷によるマストと煙突の欠損、機関と外輪を結ぶシャフトの折損による機関停止という過程を経て、12月29日午後に座礁したと考えられる。 この海難事故を詳しく分析してみると、熱帯低気圧による強風や波浪の中を無理に突っ切ったのが原因と見ていいだろう。だが劇中に描かれていた当時は気象予報体制は確立されておらず、船長も熱帯低気圧の接近を事前に予知することは不可能だったはずなので誰も責めることはできない。劇中描写から推定すると平均風速は30メートル以上、波の高さは8メートル程度あると思われる。この状況の中、船長は船を波に立てる(横波を食らって瞬時に沈没しないように船首を波浪が来る方向へ向ける)等の適切な操船を指示している。ただし劇中では操舵手が舵輪を回してもこれが効いていない光景が描かれており、この時は船が切り上がり現象(あまりの強風に船が風と水平方向にしか向かなくなる現象)を起こしていたと想像される。 座礁に至る原因は機関停止が上げられるだろう。機関が動いていればある程度は波風に抗することができ、暗礁や岩礁を避けることが不可能ではなくなる。というのは例え舵が壊れていても左右の外輪を交互に動かすことである程度の進路変更が出来るからだ。だが機関が動かなくなれば船も流されるだけになってしまい、その流れゆく方向はそれこそ風任せになってしまう。このように風浪に抗する術を全て失ってしまい、貨物を海中に投棄して重心を下げるなど保船に手一杯となってしまったこともあって海中の暗礁や岩礁に気が回らなくなってしまっていたのも事実だろう。 そして座礁時に船長が海に投げ出され行方不明になってしまい、ここで指揮命令系が崩れたのもこの船の悲運だ。座礁という事態に対して的確に判断や命令をする者がいなくなってしまい、人々は我先に脱出するという状況になってしまっていたようだ。間違いないのは救命ボートを出すに当たって誰も退船命令を出していないことだ、恐らく船員か船客の誰かが座礁を察知するとその状況も確認せずに慌ててボートを出してしまったと言うところだろう。座礁により船底の一部が破損して船室にも浸水したのは事実であるが、このケースでは船長ほどの知識がある人間なら、数日は持ちそうだと理解できたと考えられる。つまり「瞬時に沈没」という状況ではないので天候回復を待って救命ボートを出すべき状況だったのだ。座礁したままの状態で船がどれくらい持ちそうだと的確に判断できる人間がいなかったからこその悲劇である。 ちなみにこの船に残っていたのはロビンソン一家だけではない。残念ながらエドワード一家を筆頭に、船室や通路で水に流された人たちは脱出できず、そのまま船底に流されるか船外に流出するかして溺死したことだろう。 また救命ボートで逃げ出した人たちも無事とは思えない、1903年(明治36年)10月に津軽海峡で遭難した「東海丸」がこの事例に近いと思われる。青森から函館へ向かうべく吹雪の津軽海峡を横断していた貨客船「東海丸」が、津軽海峡を太平洋から日本海に抜ける形で航行していたロシアの貨物船と衝突して沈没した事例だ。この時は乗員乗客が救命ボートで船を脱出したが、折からの吹雪による大波浪で約半数の救命ボートが救助を待たずに沈んでいる。衝突した相手の船が健在でその船がすぐに救助に来てもこれなのだから、無人島が近いとは言え周囲に船舶のない状況で嵐の海に逃げ出したらどうなるか想像するのは簡単だろう。また嵐を乗り切ったら、今度は飢えとの戦いになるのもめに見えている。「タイタニック」号の場合は救命ボートで避難した人はかなりの確立で助かっている(救命ボート上で凍死した人が何人かいた)が、これは大西洋航路という当時は船が頻繁に往復していた航路上でのことであり、数時間内に救助できる範囲内に別の客船がいたからこそ助かったのである。「タイタニック」号も花形航路でない航路での事故だったら、救命ボートで逃げ出した人も多くが助からなかったに違いない。 こうして考えると、生きて船に残り、無人島に避難後結果的に生還したロビンソン一家が、この事故で一番幸せな人たちだったかも知れない。 |
|
| 第7話「なんでもできるおとうさん」 | ||
| 名台詞 | 「大失敗だ、私としたことが、考えが足りなかった。なんと言うことだ…すまない、許してくれ。私も万能じゃないんだ。失敗することもある、それも大変な失敗を…。」 (エルンスト) |
名台詞度 ★★★★ |
| 「なんでもできるおとうさん」というサブタイトルに反し、今回はエルンストの失敗が印象に残る回だ。彼は一家が生き残る道を冷静に考え、それを着実に実行していた。それは筏を造り船から脱出すること、彼は自分の知識を総動員してこの作業に当たったに違いない。その父の姿を見て「それは凄い」と持ち上げる一家だが、その家族の前でエルンストは筏を転覆させるという失敗を犯す。何で失敗したのか一家で考えているときに、エルンストが頭をかきむしりながら静かに語った台詞がこれだ。 エルンストは「世界名作劇場」シリーズの中でも万能の父親像として語られることが多いが、実は試行錯誤を繰り返して成長するキャラの一人だ。でも色々と思い付いて「試行錯誤」ができるのはいろいろな知識があるからなのは確かだ。彼は物語中盤では医師としては全く必要でない知識である造船のうんちくを語っている。その知識はこの海難事故で船に取り残されたという状況では有利に働くはずだったが、やはり彼は医師であり「造船の知識」はあっても「造船の経験」が無かったのである。その絶対的な経験不足が脱出用の筏に致命的な欠陥として現れ、エルンストは自分の経験不足を思い知ったのだ。 そしてこの失敗を「大変な失敗」としたのは、もちろん家族の生存という鍵を自分が握っていることを自覚しているからだろう。まずろくに試運転しないまま家族を乗せて出帆してしまった事で、家族を溺れさせる危機に陥れてしまった事実がある。それに筏の転覆という事実は、筏を作り直すにしろ転覆した筏を復旧するにしろ、家族が沈み掛かった船から逃げ出す時間を遅らせるという事実に他ならない。その重圧が彼の背中にのしかかっていた事を感じる部分だ。 |
||
| 名場面 | 筏の転覆。 | 名場面度 ★★★ |
| いよいよロビンソン一家は船を脱出するための筏を完成させた。特に深い考えもせず帆を張って出帆させる、ところが少し船から離れて海風をまともに浴びるようになったところで筏は突如転覆する。一家の殆どは泳げるから良かったものの、幼いジャックだけは泳げずフランツが助けることになる。そして一家は泳いで船に戻る。 嵐が去った後は、船からの脱出という当面の目標に向けて物事が順調に進んでいた。ところがこの脱出用の筏が完成したところで、一家が最初の失敗に直面した瞬間である。原因は名台詞欄に示したようにエルンストの経験不足によるものだが、それを強調するために筏制作中にエルンストが造船のうんちくを語っていたのが面白い。この流れは「いくら知識があっても経験が伴わなければ意味が無い」という教訓を視聴者に教えてくれる。こうして「なんでもできるおとうさん」というサブタイトルに反してエルンストは知識はあっても経験が伴わない男として強調され、実は「なんでもしっているおとうさん」というのが正しいことが分かる。 もちろん、このような視点でこの物語を見たのは私がこの歳になったからだ。「知識」と「経験」は全く違う、「知識」は必要だが「経験」が無ければいざというときに役に立たないという経験をしてきたからこそ、今回の物語をこういう視点で見ることが出来たのだ。この物語を見た子供達が、大人になってそれを思い知ったときにエルンストの背中を思い出してくれれば、制作者側としては大成功なのだろう。    |
||
| 感想 | 前回の続きで最後の救命ボートが去ってしまい家族が取り残されたとこから始まる。フランツの行方が分からないのに逃げるわけにはいかないと船に留まり、船と運命を共にすることに決めたシーンもなかなかのものだった。だがそのシーンは今回の本筋から外れる。もちろんフランツが見つかって感動のシーンも、その前の船長がフランツを助けて波に流されるシーンも、本筋から外れる。もちろん今回の本筋はエルンストの指示通りに皆が動き、その中でエルンストが知識人として有能であることを徹底的に印象付けた後で、筏を転覆させてエルンストには経験が伴っていないという事を印象付けることだ。もちろん要所でフローネやアンナが父を持ち上げるのも、フランツ発見の際にエルンストが的確な診断を下すのもその伏線だ。こうすることによって今後の無人島の生活でもエルンストの試行錯誤が続くことが予感させられ、さらにエルンストを試行錯誤で成長する人という人であると同時に、失敗を恐れずに物事に対処する人として描くのだろう。 前半で船長とフランツが荒海に流され、船長がフランツをマストに縛って流されるシーンがあったが、これを最後にいよいよ物語は30話以上にわたって一家5人以外の登場人物がいなくなる(亡骸と回想除く)。いよいよこの物語を印象付ける孤独な物語へと物語が流れて行くのだ。 |
|
| 研究 | ・嵐 前回は海難事故自体について考察した。今回はこの海難事故を引き起こした「嵐」について考察してみよう。 ここでの「嵐」というのは前回の考察にも書いたが、熱帯低気圧と考えられる。つまり日本でいえば台風、台風は発生地域と強さによつて名前が変わるが、南西太平洋かつ風速30メートル程度の威力があったことから「トロピカル・サイクロン」と呼ばれるものであろう。遭難場所が南西大西洋であることは物語が進むと、一家が流れ着いた無人島の位置が「東経155度・南緯10度」付近と判明することが根拠である(この厳密な位置についてはハイジの寝言様をはじめ複数のサイトで解説されていますのでここでは示しません)。 船はオーストラリアとパプアニューギニアを隔てるトレス海峡を通り過ぎ、南西太平洋に出たところで熱帯低気圧に遭遇したと考えるのが自然であろう。実は前回の嵐のシーンから船の進行方向(厳密には船首を向けていた方向)を判別するのは簡単だ。日本を襲う台風の周囲では風は反時計回りに吹くが、南半球のサイクロンでは逆に時計回りに吹くという相違がある。続いて熱帯低気圧の進行方向だが、低緯度地域における熱帯低気圧の動きは赤道から離れつつ西へ向かうというコースをとなる。つまり北半球なら北西へ、南半球なら南西へ向かう。 解説が長くなったが、「ブラックバーンロック」号が遭難した辺りでは熱帯低気圧は南西へ向かっていたことになる。平均風速で30メートルもの嵐になるとすれば、船はこの熱帯低気圧により最も風浪が強くなる場所にいたと考えるべきであろう。南西へ向かう熱帯低気圧の場合、熱帯低気圧の進行と渦巻きの相乗効果によって中心より南東側の地域が最も風浪が強くなる(東京の場合、台風が中部地方や近畿地方を横断して日本海に抜けると強風被害が増えるのはこの理由による)。その場合の風向きは東だ。嵐に巻き込まれた「ブラックバーンロック」号は船首方向から風浪を受けていたので、船首は東を向いていたことになる。 だがここで気になる事実がある、それは設定上ではこの「嵐」が5日間続いたとあるのだ。熱帯低気圧は南西に向かっていて、船は船首を東に向けているのだから、船と熱帯低気圧はすれ違う形となってそんな長時間の「嵐」を経験するとは思えない。船が熱帯低気圧の北側に回っていれば、風は西になって熱帯低気圧の進行方向と船首の向きが合うから「熱帯低気圧と船が同じ方向に進んだ」という解釈が取れるが、今度は熱帯低気圧の進行と渦巻きが風を相殺してしまうため風浪が弱まってしまう(それでも「嵐」には変わりないが、画面描写のような大嵐にはならないだろう…ちなみに東京の場合、東海上を台風が抜けた場合に雨中心となって風については意外にあっけなく過ぎてしまうのはこのような理由だ)。 悩んだ結果、「ふしぎな島のフローネ」で「ブラックバーンロック」号の海難を引き起こした熱帯低気圧は、現場付近に数日にわたって停滞したと考えられる。日本の南海上にも数日に渡って同じような場所に居座る台風があるのを天気予報で見る事があるだろう、あれと同じ事が起こっていたと解釈するのだ。しかも赤道近くで海水温が高いのだから熱帯低気圧の活動は活発になり、進行方向と渦巻きの相乗効果を考えなくともあれだけの風が吹いたと解釈することも出来る。また同時に、折からの風浪と嵐による船の破損で殆ど進まなかったと解釈すれば「停滞」説は説得力を増すだろう。ただし船首の向きは判定できない。 |
|
| 第8話「島をめざして」 | ||
| 名台詞 | 「(前略)…本当に死んじゃ嫌よ、迎えに来るまで。本当にきっと来るからね、約束するね……本当にごめんね。」 (フローネ) |
名台詞度 ★★★★ |
| 船長室に双眼鏡を探しに行った父がなかなか戻らないと皆で心配していたその頃、フローネは「忘れ物がある」と単独行動を取って船倉へ行っていた。船倉の動物を連れ出す提案を却下されたフローネは、せめて最後に餌ぐらい与えておこうと動物たちのところに行っていたのである。その際にフローネの口から出た台詞は、「餌をたくさんやるから少しずつ食べるように」「水を大事にするように」という動物への気遣いの言葉と、ここに挙げた本当に迎えに来るという約束の言葉と、自分達だけ先に脱出してしまう事に対しての謝罪の言葉だった。 フローネの動物に対する愛情と、母性がよく見える台詞だ。何が何でもここの動物たちを全部連れ出すんだという思いは、単なる子供の気まぐれではなく彼女が本当に動物たちを助け出したいと思っていたからこその思いだったことがよく分かる。数羽の鶏と1頭のロバについては筏に乗せることが認められたが、他は却下されたとは言え「後日迎えに行く」という条件の下でのことだ。だがフローネは迎えに来るまで世話が出来ない悔しさ、迎えに来る前に船が沈んでしまうのではないかと予感、自分達で逃げることが出来ずにここに縛られているだけの動物たちを置いて行くという現実、これらを受け止めてしっかりと理解していたのだろう。だからこのような形で動物たちに愛情表現をするのだ。そこに見られたものはフローネという少女の優しさであった。 この光景を見た母はフローネを抱きしめて、酒を呑んで酔っぱらった時に「悪い子」だと罵ったことを謝罪する。兄と父もこの光景を温かい瞳で見守る。このフローネの行為は今まで「生きて船から脱出する」というテーマに取り組み余裕を失っていた家族に安らぎをもたらすことにもなったことだろう。 |
||
| 名場面 | 出帆 | 名場面度 ★★ |
| 紆余曲折はあったものの、筏が一家とロバと鶏数羽を乗せて船を離れる。一家もただ筏に乗るのではなく全員に担当が割り振られ、エルンストとフランツは櫂を漕ぎ、アンナは舵取り、フローネは前方の見張り、ジャックは後方の見張りを担当することになる。こうして筏は無事に出帆し、目視されている島まで平凡な航海になると思いきや…突如「ブラックバーンロック」号の傾きが大きくなるのである。このとき船長室に閉じ込められていたジョンが部屋から飛び出し、窓から顔を出して吠える。それに気付いたフローネがエルンストに「筏を戻して」と懇願するが、ジョンの方が海に飛び込んで泳いで筏を追いかけてくる。そして筏の上で嬉しい再会となるのだ。 正常な航海だった時にあれほど印象強い出方をしていたジョンであったが、嵐が来てからは完全にその存在を忘れられていたと言っていいほど画面に出てこなかった。そして嵐→海難事故→船に孤立→船から脱出という派手なストーリー展開の中で、多くの視聴者がジョンの存在を忘れてしまっていたかも知れない。このシーンではジョンが、船客というのは飼い主である船長の客であると言う事を理解し、愛するべき存在であると認識していることが理解できるだろう。またジョンは生きて行くためにこの一家の力が必要だと言うことも、あの筏に乗らねばならないという事も気付いていたのかも知れない。 またフローネやジャックにとってもジョンという犬は単に「船長の犬」以上の友人として感じていたに違いない。だからこそフローネは「筏を戻して」と懇願するし、ジョンが筏に追いつけば精一杯の喜びを表現したのだ。この状況においてちゃんとこの犬を救ったのは意義深いだろう。 ジョンのことばかりになってしまったが、このシーンは第3話以降ずっと続いていた「船旅」のシーンが終わり、物語が新展開に入ることを意味している。いよいよ物語は、「ふしぎな島のフローネ」の中核を成す「何が起きるか分からない島での物語」へと進んでいくのだ。    |
||
| 感想 | これは子供の時の記憶でのそうなのだが、前回で筏が転覆するという展開になったがその「解決法」については次回に回された形なのでどうなるのか気になっていた記憶がある。そしたらかなり頭の良い方法で転覆した筏を復旧し、再発防止対策まで立てていることには現在も昔も感心した(筏については次回研究欄にて考察予定)。筏の転覆という難関をクリアすると一家は脱出準備を順調に進める。フローネが酒を呑んで酔っぱらったり、動物たちに餌を与えに行ったりという余裕は筏制作段階では不可能だったことだろう。物語のつくりとして感心したのは名場面欄シーン、筏が船から離れる際に一家全員が「ブラックバーンロック」号を思うだけでなく、ジョンを再登場させて効果的に使用したことだろう。これによって船からの脱出には「脱出すべきものが全部揃う」という演出効果が加わることになったと思う。 そうそう、本放送当時フローネに親近感を持ってこの物語を見ていた理由を思い出した。それは私とフローネの共通点が当時の年齢だけでなく、「3人兄妹の真ん中」という点だった。実はこのフローネというキャラは「3人兄妹の真ん中」というキャラクター性を上手く表現している。あるときは妹(弟)として兄(姉)に甘え、あるときは姉(兄)として弟(妹)に対して権威を見せなければならないという絶妙なポジションだけでなく、「家族」の中の扱われ方までフローネは「真ん中っ子」の特徴を示している。例えば今回、皆が双眼鏡を取りに行った父がなかなか帰ってこないと大騒ぎしている時に一人だけ別のことをしていて家族から存在を忘れられる辺りは、まさに「真ん中っ子」の扱われ方だろう。その中で意外な行動を取っていて家族を驚かせるのもそうかも知れない。今回はそういうシーンがあったので、私にとって「フローネ」が印象に残った理由を思い出したのだ。ちなみに「世界名作劇場」のリーズの主人公で「真ん中っ子」は他にいなかったと思う、4人以上の兄妹での中間ならばルーシーやジョオがいるが…マルコは兄しかいなかったよね? ちなみにアニメでは2人兄妹の兄という設定だったポルフィは、原作では3人兄妹の「真ん中っ子」でやはりそういうキャラとして描かれているから面白い。 |
|
| 研究 | ・「ブラックバーンロック」号難破状況について 前回から今回に掛けては、難破して座礁した「ブラックバーンロック」号船上での物語となる。熱帯低気圧の激しい風浪により機関故障を起こした同船は、操縦不能に陥って漂流した後座礁事故を起こしたという展開は前々回の研究欄に記した。ではその座礁の状況はどんなものか、これを推測してみよう。 下のキャプ画は今回の序盤に出てきた典型的な「ブラックバーンロック」号の座礁状況である。座礁からこのシーンまでの間に少なくとも1回は船体の動いたので事故直後の状況とは少し違うかも知れないが、とりあえずこのキャプ画からいろいろと推測してみよう。 まずは船体の傾きであるが、状況からして船は真正面からこの岩礁に乗り上げた様子でほぼ正確に前に31.2度の傾いたと考えて良いだろう。劇中では船が左右方向に傾いたという確証は描かれておらず、また甲板の水際線もきれいに船と直角方向に出ていることから考えても明らかだ。 第4話研究欄のキャプ画によると、この船の中心に外輪部分がある。つまりこのキャプ画によると船は後ろ半分を水中に没していることになる。第4話研究欄での推定通り、船の長さが70メートル程度と想定すると船尾最後尾部分の甲板は水面下18メートルほどのところに沈んでいることになる。もちろんこんなところまで一般人がなんの準備もなく素潜りすることは大変危険だが、するとロビンソン一家が双眼鏡を手にすることが出来なくなってしまい今後の物語に支障が出る。ここでは船体は水中に没した先で折れていると解釈すべきだ、フランツが水中の船体の様子を見た描写とは異なるが、そうでもないとエルンストは船尾の船長室にたどり着けなかったことであろう。水中に没した船内に空気が残っていると言う事は水没部分に密閉空間があるのは確かだ。 船体が折れているという解釈を取ると劇中に描かれていろいろな問題が解決する。まず船内の通路で水に流されたエドワード一家をはじめとする船客の遺体が船内にないこと、これは船体が折れたという解釈を取ればその裂け目から遺体が流出したと解釈することが可能になる。次に何度も船が振動するシーンが描かれる点、これも船体が折れていると仮定すればその裂け目から海水が流入することで後部船体の重みが増し、それによって折損部の裂け目が広がっているからだと解釈できる。一度の振動で沈まないのは、裂け目が広がっても全部船体が後方に滑り落ちる事で裂け目がふさがり、絶妙なバランスを取っていたと考えればいい。ただ今回の後半で船室にひびが入ったりするのは、いよいよそのバランスが崩れ始める前兆と受け止めることが出来る。この絶妙なバランスが崩れる時というのは、その船体の折損部が一気に崩壊したことを意味することになり、折損部の崩壊は無事だった前部船体にも海水が流入して船が沈没することを意味する…つまり「船体折損説」はこの後のストーリー展開においても説得力のある解釈だと思うが、いかがだろう? 不思議なのは座礁時にジョンが何処にいたかという問題だ。ジョンは船の振動によって閉じ込められていた部屋の扉枠が破壊され、これによって扉が開いたことによって部屋の外に出られた。従ってジョンがいた部屋は折損部に近い船体中部という事になるだろう。だがジョンは船長の飼い犬である、嵐によって船長が多忙だとすればジョンがいなければならない部屋は船長室のはずだ。しかしエルンストが「双眼鏡を探しに船長室へ行く」と言って行った場所は、海の中の後部船体だ。第4話等でも船長やジョンが船体後部の昇降口から甲板に上がってくる様子が描かれているので、船長室は間違いなく後部にあると考えて良いだろう。ならジョンが船長室にいたとすれば座礁直後に流入した海水によって溺死していたはずだ。 ジョンが何処にいたかの問題は残念ながら適当な解釈が思い付かない。船客が「嵐だから」という理由で預かっていたとしたら、その船客が部屋から逃げ出したときに一緒に船室の外に出ていたことだろう。他の船員の部屋というのも考えにくく、船長の犬を預かるような高級船員の部屋なら船長室の近くにあってやはり海の底だと考えられるからだ。飼い主が多忙になったことでジョンが迷子になったとも考えられない、そうだとしたらそれこそ特定の船室にいないだろう。 実は「ブラックバーンロック」号の謎は他にもたくさんあるのだが、これ以上考えると物語が成立しなくなってしまう面もあるのでそろそろやめておこう。  |
|
| 第9話「あたらしい家族」 | ||||||
| 名台詞 | 「いや、確かにこれはキャンプだよ。ただし永久に続くと困るがね。」 (エルンスト) |
名台詞度 ★★★ |
||||
| 島に上陸して最初の夜、未知の島とはいえ他にも人がいるかも知れないという期待感や、この島がどんなに恐ろしい島か分かっていないという事実もあって、子供達は寝る前に大はしゃぎのひとときを過ごす。それを見たアンナが「まるでキャンプにでも来ているみたい」と言うが、それに対してエルンストはこう言い捨てて夜の見張りに出て行く。 この台詞はこの一家に起きた事実を浮き彫りにしている。確かにこれはキャンプだ、家の外で火をおこしてまで文明から隔絶された生活を送るのだから。テントを立てて仮設の寝床を作り、限られた食糧で仮設の生活をするというのがキャンプというものだろう。 だがこれはレジャーでない生きるか死ぬかの真剣勝負のキャンプであることを、この台詞の後半部分とエルンストが持つ銃が物語っている。本来仮設の住まいで仮設の生活を送るべくキャンプが、現状ではいつ終わるか分からない。エルンストはこの真実をアンナに突き付けたかたちになったのだ。むろんこの台詞にある通り、永久に続く可能性もあるのだ。 この台詞の時点では、アンナは「何処かに他の人がいて助けられるに違いない」という考えが心の何処かにあったかも知れない。だから子供達のはしゃぎようを見て、自分もそれに同調するような台詞を吐いたのだ。だがエルンストは最悪の事態をも視野に入れている、それはここが無人の地であって助けを呼ぶことも期待できないという、実際にこの物語が辿ることになるシナリオだ。だからこそこのような台詞が出てくるのであり、こうやってアンナに自分の不安を訴えるのだ。 |
||||||
| 名場面 | 上陸 | 名場面度 ★★★★ |
||||
| 手作りの筏で「ブラックバーンロック」号から脱出した一家は、船から見えていた島の入り江にあった砂浜に到着する。まず父であるエルンストが銃を持って筏から下り、周囲の様子を確認してから上陸してもよいという合図の「よし」という叫び声を上げる。するとまず一番にフローネが、続いてジャックが筏から飛び降りて砂浜に向かい、続いてアンナとフランツが荷物を持って筏から下りる。 フローネとジャックは島に上陸すると、裸足のまま砂浜を駆け回る。それだけのシーンなのだがこのシーンに「長い船旅が終わり、久々に地面を踏んだ」という一家の安堵感と喜びが詰め込まれていると感じたのだ。特にフローネは「きーん」のポーズで走り回るだけでなく、砂浜に寝そべって砂の暖かさを感じるなど印象的なポーズを多く取っている。この一家の喜びが溢れてくるようなこのシーンは、船旅シーンの終わりとして強く印象に残ることになったのだ。    |
||||||
| 感想 | 物語はふたつに分かれた。前半は前回までの流れで「ブラックバーンロック」号からの脱出劇の最終編、いよいよ筏に乗って島に上陸する物語だ。後半は島に上陸して落ち着いた一家がプチクスクスの子供であり、一家のペットとなるメルクルとの出会いを描いている。どうも私の中では前半の印象が強く、後半部分は「そういやそんなこともあったっけ?」状態だった。 でも後半のフランツがプチクスクスを撃つシーンでは、思わずアムロの「撃つぞーっ、撃つぞーっ」を思い出してしまった。いや、マジで言いそうで怖かった。で撃った後は「一撃でプチクスクスを…」とか言ったりして、じゃなくてこのシーンはこの物語における初の銃の実戦使用となった記念すべきシーンだ。 それは置いておいて、前半では冷静な父の姿が印象的だ。岩礁を避けきれずに筏のアウトリガーを破壊しても、今回はへこたれることもなく前進している。また遠くばかり見ていてすぐ前を見ていないフローネを叱ったり、砂浜に到着した際に周囲の監視を忘れない冷静さは多くの子供達に「こんな父親になりたい」と思わせてきたことだろう。 反面、上陸直後に家族と一緒になって眠り込んでしまうという人間らしさも見せてくれる。考えてみればエルンストは嵐に襲われてから殆ど寝ていないはずなのだ。てーか座礁から何日経ったんだ?とこの辺りの展開を見ていて感じる。あれだけの筏を造って、一度失敗して海に沈めて、荷物を集めて筏に載せて、島まで航行して上陸するという過程を1日やそこいらでできるとは思えない。少なくとも3日くらいは掛かったと感じているのだが…。 メルクルも家族に加え、いよいよ物語は島での生活に入って行く。おっと、その前に次回でここまでの流れをまとめ物語に一区切りつけてから、新展開となって行くのだ。 |
|||||
| 研究 | ・筏 座礁していつ沈むか分からない「ブラックバーンロック」号からの脱出手段として、一家は前々回から筏を造っていた。一度作っては試運転段階で沈めてしまい、沈めた筏を引き揚げて改良するという物語を経て、一家は「ブラックバーンロック」号からの脱出を許されるのである。 筏の構造は双胴船に似たような作りだ、酒樽を浮き具として二列に並べ、その上に板を渡すという方法で一家全員の運搬と避難物資の運び出しをできる構造とした。このような構造としたのはエルンストに若干の船の知識があったためで、甲板を拡げる工夫や積載量を大きくする構造としてこのようなやり方があることを心得ていたことだろう。だが知識があっても経験のないエルンストにとって、筏の重心の問題や帆の張り方などは分からなかったり、見よう見まねだった部分もあったことだろう。これによって最初の筏は重心が高くなってしまい、また船に対する帆の大きさや位置が適当で無かったことも手伝って転覆事故を起こしてしまう。 だがこうして経験値を上げたエルンストは転覆した筏を引き揚げて、これを改造することで問題を克服する。彼が筏が横転するときの状況をしっかり把握していたのだろう、筏が「横転」したという事実から単純な横転対策を施すこととなり、筏にアウトリガーを取り付ける事でこれに対処した。この方法は成功で、改造した筏は横転することなく安全に一家と避難資材を島に送り届けることに成功する。だがアウトリガーを取り付けたことで船幅が広がってしまい、狭い入り江を航行中に左側のアウトリガーが岩礁に激突して失われてしまう。 アウトリガーとは外側への張り出しである、よくカヌーなどに取り付けられているのを見たことある方はいいることだろう。恐らくエルンストはカヌーについての知識もあったために、このプランを採ることが出来たのだと考えられる。ちなみに現在のクレーン車や高所作業車が、作業中に横転しないように横方向につっかえ棒のような物を展開するが、これもアウトリガーと呼ばれている。 また転覆した筏をどのようにサルベージするのかも気になる点だったが、船の錨を利用して揚錨機で引き起こすというのは上手く考えたもんだと、今回見て感心した。
|
|||||
| 第10話「かなしみの再会」 | ||
| 名台詞 | 「僕を助けようとして死んだんだ…船長さーん、船長さーん…」 (フランツ) |
名台詞度 ★★ |
| 上陸して最初の朝、吠えながら走るジョンを追って砂浜を行くと人が打ち上げられているのが発見される。それはその服装だけでそれと分かる人物…「ブラックバーンロック」号の船長であった。エルンストは船長の手首を掴んだだけで絶命していると判断、そしてフランツはがっくりと膝を付き、こう言いながら船長の亡骸にすがって泣く。 実はこのシーンまでフランツがどうして海に落ちたのか、何故助かったのか、誰に助けられたのか、家族の誰にも知らされていなかった。船長が身を挺してフランツの身体を流れてきたマストに縛り付け、その後波に呑まれて流されたという事実をこの時初めて家族は知ったのだ。大事な家族の一人である長男を救うために一つの生命が奪われた事実を家族全員で目の当たりにするのだが、その中でこのフランツの泣き声は印象に残るものだ。 フランツの担当は言わずと知れた古谷徹さん、もちろん「機動戦士ガンダム」のアムロ役があったからこそこのシーンを素晴らしい演技で盛り上げることが出来たのだと思う。これを見てアムロがリュウの死やマチルダの死を受けて泣き叫んでいるシーンを思い出した方も多いことだろう。このフランツ役もこの人の演技で最も印象に残っているもののひとつで、その中でも印象に残っているシーンの一つだ。 |
||
| 名場面 | 船長の葬儀 | 名場面度 ★★★★ |
| 長男を救うために生命を落とした海の男として、また一家をオーストラリアという新天地に誘うはずだった船の君主として、一家は船長を丁重に弔うことにした。座礁している船が見える岬に墓を作り、亡骸を花で飾ってから埋めて静かに祈りを捧げた。そんな中で小さなジャックは空気が読めず、明るくジャックと遊んでいるのだが…ジョンは船長の死を悲しみ、岬の突端で一人吠える。 その時、海の方から大音響が響いた。遂に「ブラックバーンロック」号が座礁した船体の痛みに耐えきれなくなって沈むところだった。フランツではないがまるで船長の葬儀を待っていたかのように…「動物たちもみんな沈んだのね、必ず迎えに行くって約束したのに」とフローネが悲痛な声で呟くと、一家は何も無くなってしまった沈没現場の方向を黙って見つめるより他はなかった。 船長の遺体発見→葬儀と船の沈没を同時に描くという展開は、物語の序盤部分の終幕を告げる印象的なシーンで、私も約30年の時を経てしっかりと覚えていたシーンの一つだ。特に墓地を作る準備をしているシーンや、船が沈んだ後のシーンをBGMも流さずに無音のシーンとしたことで、一家の悲しみをうまく強調することに成功していると思う。 またここで前々話の名台詞シーンも上手く活かしている。フローネが動物たちに「必ず迎えに来る」と約束しておきながら、それを果たせなかった悲しみもこのシーンに組み込まれているのだ。もちろん動物たちが可愛いという思いだけではない、エルンストの心中の何処かに「食糧に困るようなことがあったら船にいる鶏やブタや牛を食べることになる」という算段もあったかも知れない。もし乳牛がいれば一家の貴重な栄養源になっていたことであろう、そういう計画もご破算になってしまったという念があったかも知れないのだ。 こうして一家は外界との繋がりを完全に失った。座礁して動けないとは言え、その船が海の上にあれば誰かが助けに来るための目印にもなろう。その目印を失ったことで船が近くを通り過ぎても発見される可能性は低くなり、このサバイバル生活が長期化するであろう覚悟を強いられるのがこのシーンでもあるのだ。   |
||
| 感想 | 冒頭の船長の葬儀シーン(名場面欄)をもって、物語はいよいよ新展開へと入って行く。船長の死と船の沈没は物語に一区切り付けるためにどうしても必要だ。ここまで一家を運んできた水先案内人の死ぬという事実は心理的に「もう戻れない」という印象を強く植え付けるものであろう。船の沈没は文明社会からの孤立を意味し、ここからは何もかも一家だけの力で乗り越えなければならない状況になったことを意味している。船の上には便利な「文明の利器」が沢山積まれており、必要なのに筏で積み出せなかったであろう物も多いと想定される。特にランプの油やランプそのものは人間が人間らしく生活するための「灯り」を灯すのに必要で、船はそれを大量に使うために船がある以上はそれに苦労しないはずだった。それだけではない、食器や食べ物、それに武器や様々な工具、薬、紙やペン、服…多くの「人間が人間らしく生きるための物」がまだ残っていたに違いないのだ。「文明からの隔離」というのは、そのような物全てを失ったことに他ならない。 だからこそ船が沈んだシーンで物語が一区切り付けられる。ここまでの物語は一家が旅に出た理由から旅行中の物語と、その過程でどのように無人島に流されて文明から隔離されるかという部分が描かれたのだ。ここからは一転して隔離された状態での生活を淡々と描く物語へと変わって行く。まず最初の要素は「探検」、もちろん他に人がいないか、それとも本当は何処かの大陸の半島なのではないか?という疑問を解くための探検でもあるが、同時にこれから生活の場となるであろうこの島のことをよく知るという目的もあるだろう。もちろんこれは劇中に出てくる一家5人だけの事ではない、ここから数話の展開で見ている視聴者もこの島について詳しく知っておかねばならないのだ。そういう意味でも「探検」として島一周旅行に出かけたエルンストとフランツの行程だけでなく、テント付近の様子をつぶさに実況してくれる留守番組が見たものもチェックして置かねばならないのである。ここで出てくる要素の多くが今後の島の生活で必要になってくる。 とりあえずはフランツがまた死にかけた、それによってこの島に猛獣がいることは判明する。どんな動物なのかは今後考察しよう。 |
|
| 研究 | ・「ブラックバーンロック」号沈没 今回の序盤で「世界名作劇場」界のタイタニック、「ブラックバーンロック」号が沈没する。それだけでなく船長の死亡が確認されるなどこの船の命運がハッキリしたかたちで絶たれた状況になるのだ。 前々回の研究欄でこの船の座礁状況について考察した。劇中の描写はともかく、物語の設定や進行過程から察すると座礁した船体は中央で折れたという説を披露したが、今回は沈没について考えてみたい。 その前に前々回で書き忘れたことを追加しておこう、それは推測される船体の折損状況である。恐らく船は前方から来た波に持ち上げられ、波が通り過ぎて船体が下へと下がって行く過程で真下にあった岩礁に乗り上げたのだと推測される。その証拠に海面上に顔を出している岩礁に正面からぶつかった形ではなく、船体が上からぶつかった形で食い込んでいるのが劇中に描かれているのだ。このような乗り上げ方をすると前部船体はその場に留まろうとするが、後部船体は元の水位まで落ちようとするので船体中央部にかなりの応力が集中することになる。すると船体が横から見て「へ」の字を逆さにした形に折れ曲がることになる。こうして船体が折損し、船内に多量の水が流れ込んでエドワード一家が流されるシーンとの整合が取れるようになる。 この辺りの水深はそんなに深くないと推測されるが、水底が岩礁を頂点にした斜面になっている可能性が高い。すると折損時に後部船体が斜面になっている水底の僅かな凹凸に引っかかる事があるのだ。そうして後部船体の沈下が止まれば前部船体がその上にのしかかるように後部船体を押しつぶすことになるのだが、この押しつぶす過程で一時的ではあるが力学的に安定した点があったのだろう。結果船はそれ以上破壊が進むこともなく前部船体を水面に出したまま安定することになる。だが前部船体の重みは少しずつ後部船体を圧壊し、また水底の凹凸に引っかかっている後部船体を後方へと動かすことになる。それを数回繰り返すと折損部が前部船体の重みに耐えきれずに破壊(劇中の震動のような轟音がこれだろう)、それを引き金に後部船体の構造体が各部で破壊して後部船体はバラバラになり(劇中の大音響)、その上に前部船体が滑り落ちてくる形となる。前部船体は後部船体の破壊された構造体の上を滑りながら沈んで行くことになるるので、水底の凹凸に引っかかる事も無いだろう。こうして前部船体はついに水上から見えない位置まで岩礁を頂点とした水底の斜面を滑って行くこととなり、沈没するわけだ。もし海底を見る事が出来たならば、「ブラックバーンロック」号は水底の斜面の上側にバラバラに破壊された後部船体が、そのすぐ下には比較的原形を留めた前部船体が、並んで沈んでいる光景が広がっていることだろう。 ちなみに前部船体の岩礁に食い込んだ部分がブレーキになったとは考えにくい、それだと前部船体の破壊が大きいことになって水の流入が止まらずに短時間で沈むことになるのだ。逆に破壊が少なければ沈むことはなく、ずっとあの位置で座礁したままであろう。だからこそ船体折損説は説得力があるのだ。 あとの謎は救命ボートと海へ流出した船客がどうなったか? 風は船の正面方向から吹いていたから救命ボートは島と逆方向に流されたと解釈することは可能だ。ただ島に流れ着いた遺体が船長だけというのはちょっと不自然だ。恐らく一家が岩場ばかりだと上陸を諦めた海岸線に、船内で水に流されて船体折損部分から海へ流出した船客や乗組員の遺体が流れ着いていたと考えられる。陸上から到達困難な場所が多そうな島だから、この解釈も説得力があるだろう。  |
|



